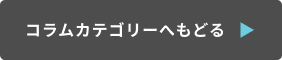育休中の給料はいくらもらえる? 受給条件・期間など

育休を取得し仕事を休んでいる間は、会社からの給料はもらえないことが一般的です。その代わりに、育休手当と呼ばれる制度を利用すると、雇用保険から一定の給付金を受け取れます。
この記事では、育休中の給料についての知識や、育休手当の金額の計算方法、受給できる条件、申請方法などについて解説します。育休の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
育休と給料について
まずは、育休の概要や育休中の給料について見ていきましょう。
育児休業とは
育児休業は、育児・介護休業法によって定められている制度です。1歳未満の子どもを育てる人のための制度で、勤め先の企業に育児休業申出書を提出することで休業を取得できます。
育休中は給料が支払われないことが一般的
育休中は仕事を休んでいる状態となり、給料は支払われないことが一般的です。ただし、育休中の給料の扱いは企業によって異なるため、勤め先の就業規則を確認してみましょう。
育休手当の申請をすれば給付金がもらえる
育休手当は、「育児休業給付金」という制度の一般的な呼称です。一定の条件を満たす労働者が申請を行うことで、育休中に給付金がもらえます。
育休手当(育児休業給付金)の金額の計算方法
育休手当の金額は、休業開始前の6か月間の給料を180で割った「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。具体的な計算式は「休業開始時賃金日額×支給日数×給付率」となります。給付率は、育休取得から180日までは67%、それ以降は50%に設定されています。
休業開始時賃金日額には上限額と下限額があり、令和7年7月31日までの上限額は15,690円、下限額は2,869円です。ただし、上限額と下限額は改訂される場合があるため、厚生労働省による最新の資料を確認しましょう。
育休手当(育児休業給付金)を受給できる条件
育休手当を受給するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
雇用保険の被保険者であること
育休手当は、雇用保険と呼ばれる制度によって支給されるものです。そのため、雇用保険の被保険者であることが育休手当を受給する条件となっています。
原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得していること
原則として、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に、育休手当の受給が可能です。
ただし、「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる制度を利用して育休を取得する場合には、1歳2か月に達する日まで育休手当がもらえます。さらに、保育所での保育が行われない場合などは、1歳6か月または2歳までの育児休業取得で、育休手当の受給が認められます。
育休開始日の前2年間に所定の賃金支払基礎日数があること
賃金支払基礎日数とは、賃金の支払い対象となる労働日数のことです。育休開始日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上、あるいは就業時間が80時間以上だった月が12か月以上ある場合に、育休手当を受給できます。
また、条件を満たす月が12か月未満の場合であっても、第一子の育休などにより30日以上にわたって賃金が支払われなかった期間があれば、育休手当を受給できる可能性があります。
育休開始日から1か月ごとの就業日数または時間数が所定の要件を満たすこと
育休を開始した日から1か月ごとの期間について、就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下であることも、育休手当を受給するための条件です。
育休手当(育児休業給付金)を受給できる期間
育休手当を受給できる期間は、原則として子どもが満1歳になるまでです。法的には誕生日の前日に満年齢に達したとみなされるため、誕生日の前々日が育休手当を受給できる最終日となります。
ただし、子どもが満1歳になるよりも先に育休を終えて復帰した場合には、復帰日の前日までが育休手当の受給期間です。また、所定の条件を満たす場合には、最長で子どもが2歳になるまで受給期間を延長できます。
育休手当(育児休業給付金)の申請方法
育休手当を申請する際は、まず勤め先に育休を取得する旨を伝えましょう。その後、勤め先からハローワークに対して必要書類を提出し、受給資格が認められると、支給決定通知書の交付や育休手当の給付が行われます。
育休手当の申請に必要な書類には、勤め先が用意するものと、受給者本人が用意するものがあります。
勤め先が用意する書類は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、育休の開始日や終了日、賃金の支払い状況などを確認できるタイムカードや賃金台帳などです。
受給者本人は、育児を行っていることを証明できる母子健康手帳や、医師の診断書、出産予定日証明書などを用意する必要があります。
勤め先の総務部や人事部の担当者に相談した上で、育休手当の申請を進めましょう。
まとめ – 育休中は給料の代わりとなる育休手当を受給しましょう
育休中は、ほとんどの企業で給料が支払われません。その代わりに、国の制度である育休手当を申請すると、給料をもとに計算された給付金が一定期間もらえます。
育休手当の受給条件は、雇用保険の被保険者であることや、原則として1歳未満の子どもの養育のために育休を取得していることなどです。
また、男性の場合、2021年から始まった出生時育児休業制度(通称:産後パパ育休)により育休を取得する事ができます。赤ちゃんの出生後8週間以内に最大4週間の育休を取得でき、育休期間中は、雇用保険から給与の67%相当が支給されます。
育休手当を受け取りたい方は、勤め先の総務部や人事部に相談の上、必要な手続きを進めましょう。