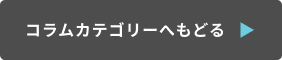業務委託とは? メリット・デメリットや雇用契約との違いについて解説します。

働き方が多様化している昨今、「業務委託」という働き方に興味を持っている人もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は「業務委託」という働き方について、特徴やメリット・デメリット、契約締結時の注意点などを解説します。
業務委託とは?
まずは業務委託とはどのような働き方なのか、定義や雇用契約との違いについて解説します。
業務委託の法律上の定義
「業務委託契約」という言葉は、法律上で具体的に定義されていません。
業務委託に関連する契約形態として、民法632条の「請負契約」、643条の「委任契約」、656条の「準委任契約」があります。
しかし、ビジネスの現場での業務委託契約は多様なケースがあり、単にこれらの契約に当てはめるだけでは対応が難しいケースも少なくありません。そのため、契約ごとに内容を細かく定め、契約先の会社と詳細な取り決めを行うことが重要です。
業務委託のフリーランス新法での定義
2024年11月1日に施行となる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」において、「業務委託」とは「事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する行為」と定められています。
つまり、業務委託とは企業が業務の一部を外部の個人や企業に委託することを意味します。
業務委託と個人事業主の違い
業務委託と個人事業主は関連性のある言葉ですが、概念としては異なります。
業務委託は、企業が特定の業務を外部に依頼する契約形態を指します。
契約の種類としては、「請負契約」や「委任契約(準委任契約を含む)」があり、業務内容や作業の進め方、責任の範囲が契約内容によって異なります。業務委託契約を結ぶのは、企業とフリーランス、法人、または個人事業主など、さまざまな形態の事業者です。
一方、個人事業主は、法人を設立せずに個人で事業を運営する働き方の形態を指します。個人事業主は、業務委託契約を結んで仕事を受けることが一般的ですが、それ以外にも直接クライアントと取引したり、独自の事業を展開したりすることもあります。税務上は、確定申告を行い、必要に応じて青色申告を活用することで、経費の計上や節税対策を行います。
雇用契約と業務委託契約の主な違いとは?
雇用契約とは、正社員や契約社員、パート、アルバイトのように、決められた時間分の労働力を提供し、その対価として報酬が支払われる雇用形態です。「雇い主」と「従業員」という主従の関係となり、「雇い主」は仕事の進め方や勤務時間などにおいて指揮命令権を行使できるようになります。また、労働者を保護する労働法が適用されます。
一方で業務委託契約は、雇用契約とは違って企業との雇用関係がないため、委託元に業務の指揮命令権はありません。また、労働基準法も適用されません。
業務委託として働くメリット
業務委託として働く主なメリットを4つ紹介します。
自由度の高い働き方が可能
業務委託は働く場所や時間を自分自身で選んで働けるため、自由度の高い働き方を実現しやすいといえます。労働時間や業務量、スケジュールも自分の裁量で調整できるため、家庭や趣味との両立など、ワークライフバランスの実現も目指せます。また、複数の企業と業務委託契約を結ぶことも可能です。特にリモートワークが可能な業種では、さらに柔軟な働き方が可能になるでしょう。
高収入が得られる可能性がある
業務委託は仕事を請け負った分だけ報酬を得られる働き方なので、十分な量の仕事を請け負えば高収入を得られるチャンスがあるといえます。また、専門的な知識やスキルが求められる業務では、より高額な報酬を得られる可能性があるでしょう。
企業側にもコスト削減などのメリットがある
一時的に発生する業務や専門的な業務などを担う人材が必要になった際、新たな人材と雇用契約を結んだり新しい部署を作ったりすると、さまざまな費用が発生します。しかし、業務委託契約によって委託先に必要な業務を依頼することで、採用や教育にかかるコストを削減できます。
幅広い経験を積むことができる
業務委託は、幅広い経験を積めるというメリットがあります。異なる業界や分野の仕事に携わることで、新しいスキルを習得しやすく、専門性を高めるチャンスもあるでしょう。また、自分のスキルを活かして特定の分野での実績を積み重ねることで、市場価値を高めて次のキャリアにつなげることも可能です。
業務委託として働くデメリット
業務委託として働く主なデメリットを3つ紹介します。
社会保険の非適用や自己負担のリスク
業務委託の場合は雇用契約とは異なり、企業側は社会保険や雇用保険を負担してくれません。雇用契約の場合は保険料を折半して企業と従業員がそれぞれ負担しますが、個人事業で業務委託として働く場合の社会保険は全額自己負担となります。
また、健康保険未加入の期間に病気やケガなどをした場合、医療費は全額自己負担となってしまいます。
偽装請負のリスク
偽装請負とは、業務委託の契約形態であるにもかかわらず、委託元が委託先の受注者に対して直接指揮命令を行うなど、実態としては労働派遣に該当するような状況のことを指します。
偽装請負は違法とされており、偽装請負に該当すると判断された場合は罰則が適用される恐れがあります。罰則は発注者と受注者の双方に適用されることもあるため注意が必要です。
損害賠償が発生するリスク
業務委託契約では、業務の遂行に関する責任が委託先にあるため、業務の不備や契約不履行が発生した際には、損害賠償責任を負うリスクがあります。
特に、請負契約では成果物の納品が義務付けられるため、品質の不備や納期の遅れが損害賠償の対象となる可能性があります。一方、委任契約や準委任契約の場合、成果物の完成義務はないものの、故意や過失によって損害を与えた場合には責任を問われることがあります。
こうしたリスクを軽減するには、契約書に損害賠償に関する条項を明記し、責任の範囲を明確にしておくことが重要です。特に、損害賠償の上限や免責事項を定めることで、万が一の事態に備えることができます。
業務委託を受ける際には、契約内容を慎重に確認し、必要に応じて弁護士に相談したりコンサルティングを受けたりするなど、リスクを最小限に抑える対策を講じることが大切です。
さらに、情報漏洩や知的財産権の問題にも注意を払う必要があります。
特に、著作権や個人情報の取り扱いに関するルールを契約で定め、リスクを回避するための対策を講じることが重要です。データの管理やセキュリティ対策を徹底し、社会的信用を損なわないよう努める必要があります。
業務委託における契約の種類と注意点
業務委託における契約の種類や注意点、フリーランス新法による影響について解説します。
請負契約と委任契約の違い
業務委託には「請負契約」と「委任契約」の2種類があります。
請負契約とは、成果物を完成させて納品することで、依頼主から報酬が支払われる契約形態です。
委任契約は、契約した期間や場所において、指定された業務を遂行することで報酬が発生する契約形態です。医師や弁護士、不動産業など、法律行為を扱う業務については「委任契約」、それ以外の業務については「準委任契約」と区分されます。
契約締結時のポイントと確認事項
業務委託において契約書の取り交わしは任意であるものの、口頭やメールでのやりとりだけではトラブルにつながる恐れがあるため、きちんと業務委託契約書を締結したほうがよいでしょう。
契約書を確認する際には、実施する業務範囲や内容、報酬について、相違なく明記されているかを十分に確認することが大切です。また、報酬については金額だけでなく、支払条件や支払日、支払い方法などについても詳しく確認しておきましょう。
権利や義務に関しても、対象事項とその範囲などの取り決めについて明記してあるかを確認することが大切です。
フリーランス新法による影響(2024年11月施行)
2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」、いわゆるフリーランス新法は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備することを目的としています。
発注事業者からフリーランスへの業務委託において、取引による不利益を防ぐことや、トラブルの際に泣き寝入りせずに済むようにすることなどが定められています。
ただし、フリーランスが必ずしもすべての状況で保護されるというわけではないため、フリーランス新法の内容を正確に把握して、契約書を十分に確認したうえで業務を行うようにしましょう。
業務委託と相性の良い職種
業務委託と相性の良い職種には、経験やノウハウ、高度な専門性が求められるものや、プロジェクト単位での業務が多い職種が挙げられます。特に、インターネットを介したオンラインでやり取りを行うことの多い職種と相性が良いと言えるでしょう。
コンサルタント
経営、IT、人事、マーケティングなどの分野で専門知識を提供する職種です。プロジェクトごとの契約が多く、業務委託の形態が適しています。
デザイナー
グラフィックデザイン、Webデザイン、UI/UXデザインなどのクリエイティブ業務は、プロジェクト単位での受注が一般的であり、業務委託が適しています。
システム開発
エンジニアやプログラマーとして、アプリ開発やWebシステム構築、ソフトウェア開発を行う職種です。案件ごとの契約が多く、フリーランスや業務委託の形態で働く人が多いです。
ライター・編集者
記事作成やコンテンツ制作、書籍編集などを行う職種です。Webメディアや企業のコンテンツ制作で業務委託の需要があります。
マーケティング・SNS活用
企業のマーケティング戦略立案やSNS運用、広告運用を請け負う職種です。プロジェクトベースでの業務が多く、業務委託の形態が一般的です。
動画・映像編集
動画制作や映像編集、アニメーション制作を行う職種です。YouTubeや企業のプロモーション動画制作などで業務委託の需要が高まっています。
翻訳・通訳
多言語対応が求められるビジネスでは、翻訳・通訳の業務委託契約が多く結ばれます。
業務委託で働く際の注意とポイント
業務委託として働く場合、求める仕事を獲得するためには、得意分野を明確にし、案件を探しながら適切なリソースを活用することが求められます。特に、デザイナーやシステム開発、コンサルタントなどの分野では、実績を積み重ねることで市場価値が高まり、案件の単価向上が期待できます。
効率的な業務のための工夫を行う
業務効率化を図るために、タスクマネジメントツールを導入し、業務プロセスをスムーズに進めることも重要です。具体的には、スケジュール管理やリモートワークの環境整備、税理士への相談などを通じて、業務の安定性を確保することが大切です。
営業活動においては、SNSやWEBサイトを活用したマーケティング戦略を取り入れることで、新たな案件の獲得がしやすくなります。
長期的な視野でキャリアを検討する
また、キャリアアップの観点からは、研修やセミナーに参加し、スキルを向上させることが不可欠です。業界の動向を把握し、成長を目指すことで、自身のポジションを強化し、多様化するビジネス環境に対応できるようになります。
安定した収入の確保
業務委託の働き方は自由度が高い一方で、収入の変動が大きく、契約解除や案件の減少といったリスクが伴います。そのため、長期的な安定を目指す場合、定期的に案件を受注できるよう、営業活動を継続することが重要です。また、契約期間の明確化や支払いのルールを契約書に記載し、経理処理を適切に行うことで、経済的なリスクを軽減することが大切です。
まとめ – 業務委託のメリット・デメリットを知っておきましょう
業務委託は自分の裁量で働くことが可能で、働き方次第では高収入も目指せる場合があります。社会保険などの仕組みも踏まえてメリット・デメリットを正しく理解し、自分に合った働き方を見つけましょう。